お知らせ
少し遅くなりましたが、2024年本年もよろしくお願い致します。
今年も動物ファーストな治療を提供できるように邁進していく所存です。
1月の臨時休診日・診療時間変更のお知らせです。
1/27(土)10:00〜診療開始 とさせていただきます。
1/29(月)・30(水)終日休診となります。
スタッフはおりますので、物品のお渡しや電話でのご相談は可能です。
午前10〜13時・午後15〜17時の間にご連絡下さい。
夜間診療も休診となりますので、ご了承下さい。
あいす動物病院 院長 高橋
ブログ
あいす動物病院院長の高橋です。
皆様におかれましては平素より当院へのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、4月からペットホテルの料金体系を変更させて頂く事となりました。
昨年の1年間を踏まえて、院内で検討を重ね、普段からご利用頂いている飼い主様からのご意見も頂戴し、ペットホテル料金は見直しをしました。
まず、日割りで1日ごとに計算していたホテル料金を、今後は1泊2日料金と以降1泊ずつの料金加算とすることと致しました。
これにより、朝9時からお預かりさせて頂く場合でも、夕方からお預かりになる場合でも、差が出にくくなると考えております。
お預かりの際の予防などのルールは大きく変更はありません。
その他の変更点としましては、ジェネリックの医薬品・動物用医薬品など院内で採用している医薬品の見直しをすることで、薬価の改定をさせて頂きました。
また、逆に今回の改定で食事療法食やワクチン・検査などは輸入による原価高騰がありましたので調整させていただく事となります。
詳細につきましては、電話・メール等にてお問い合わせ頂くか病院受付にてご説明致します。
何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
あいす動物病院 院長 髙橋一馬



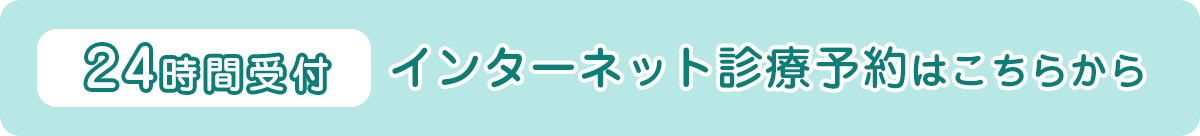
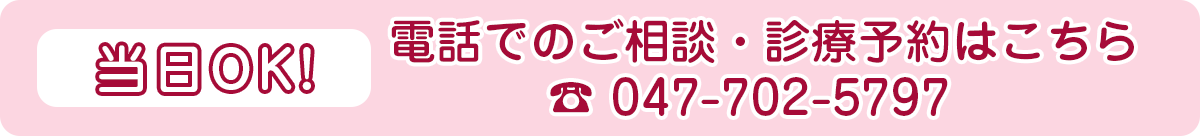
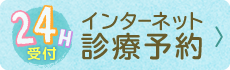

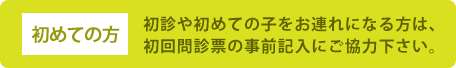
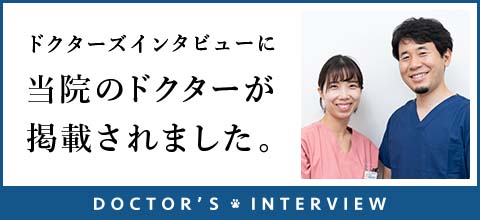


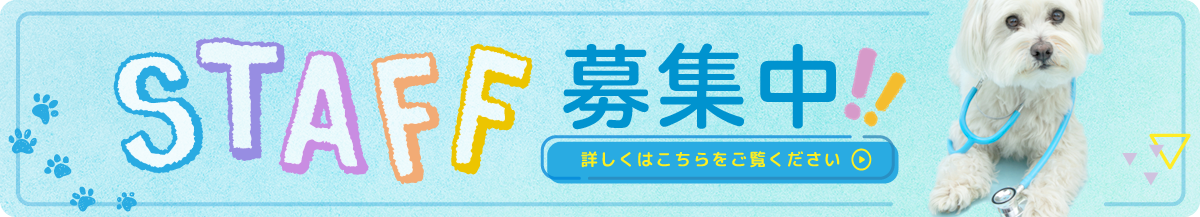


































 電話をかける
電話をかける WEB予約
WEB予約